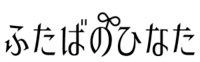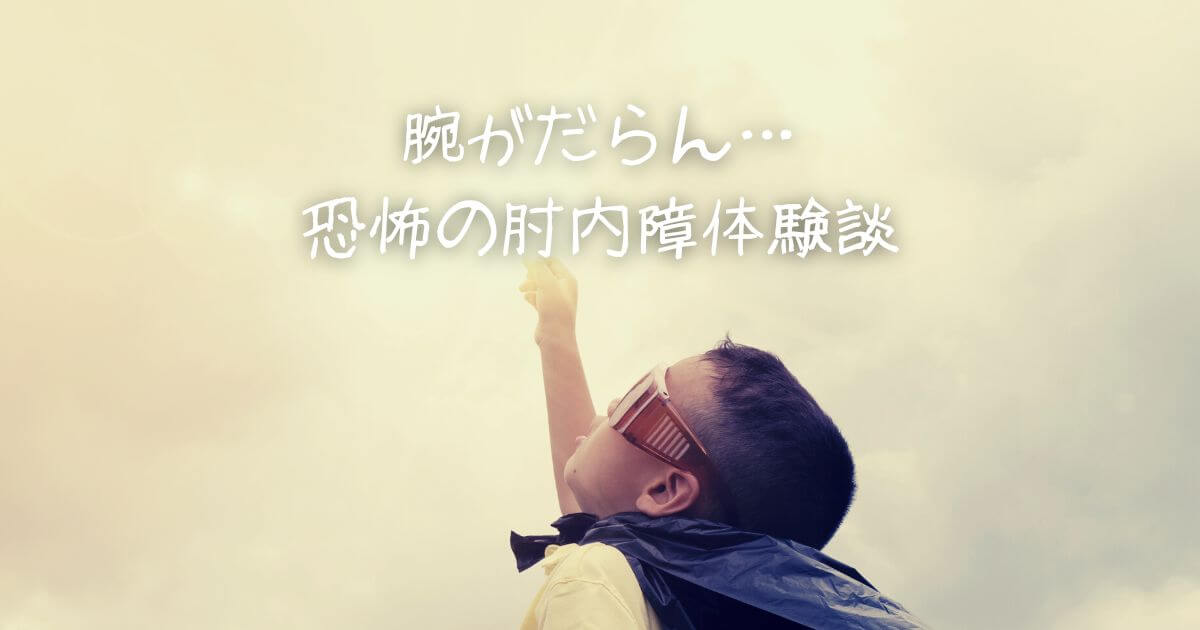先日、1歳7ヶ月の息子の腕が上がらなくなって、救急病院にかけ込む事態に…!
診断されたのは「肘内障」
私は初めて聞いた怪我の名前でしたが、「子供にはあるあるの怪我」なんだそうですよ。
ということで、この記事では肘内障になった経緯から整復まで。
その後繰り返したかなど、一連の記録を書いておきたいと思います。
子供の腕がだらん…脱臼?骨折?え?【肘内障体験談】
肘内障(ちゅうないしょう)は、肘の輪状靭帯と橈骨頭がはずれかける、いわゆる亜脱臼を起こしている状態のことです。 親がこどもと手をつないで歩いているとき、子どもが転びそうになりとっさに手を引っ張って起こるなど、歩き始めから小学入学前までの子どもに多いです。
引用元|おおつか整形外科BLOG
イヤイヤ期真っ只中の1歳7か月の息子と2人目妊娠中の私。
お散歩の帰り道、家まであと少し…で、事件は起きた・・・!
何事!?顔を真っ赤にして泣きやまない
家まであと数メートルなのに、、大号泣でイヤイヤ発動。
私と手を繋いだまま、息子が勢いよく地面に倒れ込んだんです。

危ない!と私もその時思わず手を引いたのだと思います...。
すると直後から、火がついたように泣き出す息子。
今まであまり見たことが無いような泣き方で、慌てて抱っこして家へ連れて帰りましたが、中々泣き止まなかったんです。

顔真っ赤にして泣いてた…!
どっか怪我したのか?と思って様子を見てみると、
左腕がだらんとなって腕が上がっていないことに気が付きました・・・!
(反対の手でだらんとなった腕を押さえてる...)
(しかも私が左腕を触ろうとすると嫌がる)
脱臼?骨折?演技!?なに!?色んな可能性が頭を過るw
本当に腕が上がらないのか見るために、大好きなお菓子を渡してみましたが、やはり左腕は動かせない・・・
これはマジのやつだ!とプチパニックになりました。
まさかの救急病院へ~整復まで~
どういたらいいか分からず初めて小児救急電話相談事業(#8000)に電話!
が、時間外というバッドタイミング(;;;°;ω°;):
もう一つ聞いたことがあった「病院に行くか迷った際に相談できる電話窓口(#7119)※一部地域での実施」に電話すると、泣き止まないなら病院へ行った方が良いですと言われ、近くの救急病院を案内して頂きました。

この日はちょうど日曜日。近くの小児科や整形外科などは開いておらずでした...。
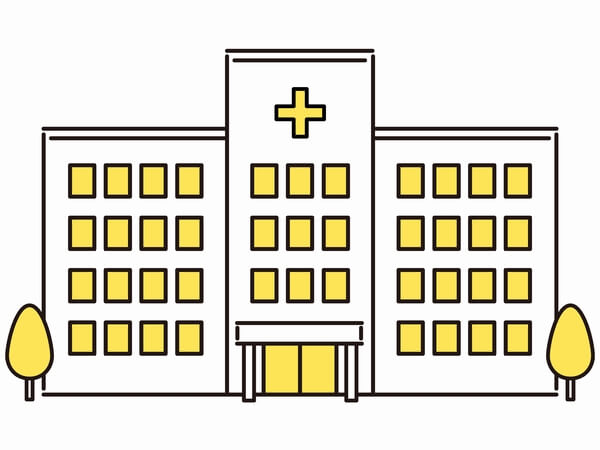
タクシーで救急病院へ到着!すぐに診察室で診てもらえました。(この間も息子はギャン泣きです)

腕がはずれかかっている「肘内障」ですね。すぐ治せますよ。
で、驚いたのが、
1・2・3・ハイッ!
で肘をグイッと整復して下さって、たった3秒で治ったこと。
顔真っ赤にして泣いていた息子もそのあとピタッと泣き止むもんだから本当驚きました...!
看護師さんに怒られた!
腕がちゃんと動くか、問題ないか確認して頂いて、ホッと一息ついていたところ…

「子供の腕は引っ張らないこと!」
年配のベテランっぽい看護師さんに怒られた:((((;´・ω・`)))
別にわざと引っ張ったわけじゃないし...
危険なときは親として手を引いちゃうこともあるじゃないか...
と思いながら、その時は何も言葉が出なかった。。
救急病院のお会計を待っているとき、
やっと泣き止んで遊んでいる息子を見て、緊張の糸が解けたのか、恥ずかしながらちょっとだけ泣いちゃいました( ;ᵕ; )w
ちょうどつわりがひどかった時期でもあったので、
ずっと息子を抱えながらあたふたして、本当大変な1日でした...(1番大変だったのは息子なんだけどね)

こんな時に限って夫は友達と出掛けていて不在というね、、
肘内障は自分で整復しない方がいい
友人のママにこの一連の話をしたら、あるある~~~と。
友人の子供はクセになってしまったらしくよく繰り返したので、なんとその都度友人が整復したっていうんです...!
(調べたら素人がやることで筋を傷めたり悪化することもあるとか…)
怖すぎて私には無理><
やっぱり専門家に診てもらった方が安心と思ったので、我が家はいつなっても対応できるよう、
近所の整形外科や接骨院などメモして冷蔵庫に貼っていました。
肘内障を診てくれる小児科もあるらしいですが、骨折やヒビの場合もあるので、基本的には整形外科や接骨院で診てもらうのがいいらしいですよ
追記①その後肘内障を繰り返すことは無かった
肘内障は、関節や靭帯が未完成な5歳くらいまでは再発しやすいそうです。
が、我が家の息子、現在6歳ですが1度も再発していません!
道路などで危険なときはある程度手を引くこともありましたが、繰り返すことがなくて良かったです。
追記②保育園で聞かれた!肘内障は記録しておくべし

肘内障について油断していたことですが、
保育園の面接時に「肘はずれたことありますか?」と聞かれたんです・・・!
というのも、保育園では肘内障はあるあるで、
友達同士遊ぶ中で手を強く引っ張りすぎて外れることってあるあるなんだとか...。
1度外れたことがある子は繰り返すことがあるから、
- 今まで外れたことはあるか
- どちらの腕か
- かかりつけの整形外科や接骨院
このあたり保育園側は詳しく把握しておきたいそうなんです。
息子が肘内障になったのは1歳。
私もすっかりどっちの腕だか忘れてしまっていたのですが、この記事にちゃんと記録しておいて良かったです(笑)
今では母子手帳の病気や怪我など書けるページにしっかりと書き込んでおきました((`・∀・´))b